【進藤君枝さん・73歳】『インシャラー』——明日のことはわからない
最愛のパートナーとの死別で得た死生観

取材・文:出口夢々
60年生きた女性にはいろいろな人生がある。そして、女性一人ひとりはそれぞれ自分の人生を背負い、生きている。若くして家庭を持った人、働きながら子どもを育てた人、社会で戦い抜いた人——。そんな女性たちが経験した、人生の「酸い」も「甘い」を紹介する連載企画「60年、酸いも甘いも讃えたい」。
第4回目は、東京都港区にお住いの進藤君枝さん(73歳)にインタビュー。異国の地・イランで幼児教育の職に就いた経歴や、最愛のパートナーとの出会いと死別、国内外を旅した経験について話を伺った。
東京都港区にお住いの進藤さん。生まれも育ちも虎ノ門。約30年間従事した幼児教育の職を退職し、終の棲家として選んだのも虎ノ門の家だ。
パン屋を営んでいた実家は、現在、虎ノ門ヒルズが建つ場所の一角にあった。進藤さんが学生だったころ、日本は高度経済成長期の真っ只中。近隣に建つ小さなオフィスビルも活気に溢れ、進藤さんの両親がつくるパンやサンドイッチは飛ぶように売れた。進藤さんも学校に行く前には、ホットドックを150本、食パン10本分のサンドイッチをつくり、商いを手伝っていた。
「私も学生時代が終わり、しばらく経った後、虎ノ門ヒルズの建設が決まり、実家の土地が買収されることになったんです。等価交換として代金か新しく建つマンションの一室を受け取れると言われて、マンションを選びました。今暮らしているマンションはそのとき手に入れたものなんです。でも、友人たちに『進藤さんを捕まえるの大変』と言われるほどお出かけが好きで、家にいる時間は短いんですよ」

そう語る進藤さんは、国内外問わず、さまざまな土地へ足を運んできた。新型コロナウイルスの感染が拡大した今でこそ旅行を控えているが、京都や沖縄、青森、はたまた海を跨いでキューバなど、思うままに旅している。
「キューバを旅したのは去年の夏のことでした。クラシックカーに乗っている写真を撮ってもらいたくて行ったんです。ツアーで行ったんですけど、参加しているのは若い人たちばかりだったので、1人で参加しているお年寄りの私にみんなやさしくしてくれて(笑)。わからないことがあったけど、まわりの人に教えてもらいながら旅行しました」
自ら格安航空券を手配し海外へ行ったり、クルーズ船にも1人で乗船し海外を周遊する進藤さんがはじめて海を渡ったのは、20歳のときのこと。最初に訪れた国はフィリピンだ。
「安い金額で行けたので、母や妹と一緒によく遊びに行っていましたね。それからヨーロッパにも行くようになったのですが、ツアーを予約してヨーロッパに行く妹たちを傍目に、私はパキスタン航空の安いチケットを買って、リュックを背負って行っていました。外国に何度も足を運んでいるのは、日本よりもそっちのほうが自分の気質に合った土地だなと思ったから。次第に、外国で生活したいなあ、と思うようになりましたね」
1977年4月、その想いを胸に進藤さんはイランの首都・テヘランへと旅立った。大学で幼児教育を学び、幼稚園に勤務していた進藤さんは、テヘランの日本人幼稚園で園長を務めることになったのだ。29歳のときのことだった。
「海外で暮らしたいなと思って、海外にある日本人学校に片っ端から手紙を書いて、幼稚園の先生の口を探しました。結局、知り合いの先生に推薦状を書いていただいて、やっとテヘラン行きが実現したんです。明るくて楽しい人が多いテヘランでの生活は、『いつまでもここで暮らしたい』と思わされるものでした」

「イラン人はいい加減なところもあって、何かあるとすぐに『インシャラー』(日本語で「神のみぞ知る」の意)と言うんです。『明日のことはわからない』という調子で暮らしている人が多かったと思います。現地の女性はあまり外出しないようでしたけど、私はいろいろなところを歩いてまわりましたね。テヘランで知り合ったインド人女性がイスファハンに引っ越したときには、夜行列車で10時間かけて会いに行ったりもしました。車窓から街の様子を眺めるのが好きなんです」
進藤さんがイランで暮らしていたのは、1977年4月から1980年3月までの3年間。当時のイランでは革命が起こっており、情勢悪化により進藤さんは帰国することになった。オリエンタルで華やかな側面を持ちながらも、社会は混沌としている——。そんなイランで進藤さんが出会ったのが、生涯をともにすることになるパートナー・佐々木敏夫さんだ。佐々木さんも単身でイランに渡り、現地で働いていた。
「佐々木さんとはパーティーで出会いました。共通の知人が何人かいたので、顔を合わせることが多かったんです。そんなことから親しくなりました。私は31歳で、彼は47歳。私は自由気ままな独身でしたが、彼は日本に家族を残して単身赴任をしている身でした。互いに、異国の地において1人きりで生きていたので、寂しさを抱いているなど交際にいたる要因があったわけですが、『すっかり燃え上がってしまった』というわけではなく……むしろ、淡々とした恋だったと思います」
「彼の家は下町のほうにあったので、山の手に住んでいた私がそこまで出て行って、2人でよくチャイハネ(喫茶店)でお茶をしていました。下町の市場に行って肉を手に入れ、私が料理をしたり、休日には山を越えてカスピ海の近くまで行き、スーフという淡白な味の魚料理を楽しんだり。彼とは16も歳が離れていましたが、気が合ったんです。私は勝気なところがある一方、気が小さいところもあって。物静かで責任感のある彼は、そんな私をしっかりと支えてくれていました」
しかし佐々木さんは既婚の身。離婚調停は成立せず、進藤さんとは生涯、内縁関係のままだった。結婚して、佐々木さんとともに日常を送りたい——。進藤さんは幾度とそう願ったが、叶わなかった。
進藤さんは1980年に日本に帰国後、佐々木さんの次の赴任地として候補に上がっていたアメリカへ、一足先に足を運んだ。幼児教育を学ぶスクールに入学し、佐々木さんが赴任してくるのを待っていたのだ。しかし、佐々木さんはオーストラリアへの赴任が決まる。
「このころ、悲しくなるとよく国際電話をかけて泣きました。『もうダメ』と伝えると、彼は『僕も同じだ。ここまで来たのだから、行くところまで一緒に行こうよ』と言うんです。そのまま結局、私たちは関係を続けることになりました。アメリカから帰国したあと、オーストラリアで彼と再会した際に『なんだか知らないけど、こんなに安定した気持ちになったのははじめてだよ』と言ってくれたことが、今でも心に残っています」
進藤さんは日本に帰国したあと、再び幼児教育の職に就いた。1982年からは主任として幼稚園の教育改革に踏み切る。
「お揃いのエプロンを着用させ、子どもたちに同じことを一斉にやらせる。 ‟統一” を大事にする園だったのですが、私は子どもたちの自由を大切にし、自主性を育てることに重点を置いていました。依頼があって行った改革でしたが、私が赴任する前にいた先生たちからの抵抗も大きくて。幼児教育に対する根本的な考え方のぶつかり合いでもあったので、とても苦労しましたね」
その幼稚園で7年間主任を務めた後に、進藤さんは一度退職。佐々木さんが赴任していたインドやカナダへ足繁く通い、2人は愛を育んでいった。進藤さんは、1995年から園長として再度、幼児教育の職に就き、17年間勤め上げる。だれでも遊べるように園庭を解放したり、保育時間中に未就園児親子を受け入れるクラスを設立したりと、次々に園に改革を起こしていった。その間に佐々木さんも最後の赴任地・カナダから帰国し、退職。2人でマンションを購入し、落ち着いた暮らしを送り始めた。
「まだ私は仕事をしていたので、平日は家でゆっくりして、週末には国内各地へと足を運びました。春休みや夏休みには海外に行って、のんびりするのが習慣でしたね。彼が退職してからの約19年間は旅行尽くしでした」

長年の通い婚が終わり、ようやく手に入れた安らかな暮らしを満喫していた2人。しかし、2011年に佐々木さんがてんかんの発作を起こしてから、進藤さんの看護生活が始まる。
「彼が家から遠い病院に入院することになったので、往復2時間かけて毎日病院に行っていました。当時、私はまだ働いていたので、面会できるのは就業後。週末には病院近くのビジネスホテルに泊まり、会いに行っていました。限られた時間ではありましたが、『彼のところに行きたい』という一心で病院に通っていましたね。すぐにでも退職して看護に力を注ぎたかったのですが、なかなか後任の先生が見つからなかったので、仕事と看護をする生活が2年間続きました」
園長として務めなければならない仕事をこなし、後のことは先生方に任せ、自分は病院へ向かう――長年従事してきた幼児教育の職をないがしろにするような行為に途方に暮れることもあったが、「こうするしかたなかった」と進藤さんは語る。
「そのときは無我夢中でしたよ。彼はその後認知症になったので、病院から家の近くのホームに移り、介護生活が始まりました。だんだんと彼の意識がはっきりしている時間が短くなっていったのですが、意識が正常なときには2人で会話を楽しんだり、音楽を聴いたり、ビデオを観たり——心安らぐ時間を過ごしました。ですが、最後は衰弱で亡くなってしまったんです」

最愛のパートナーを失った進藤さん。任意後見契約を結んでいたものの、戸籍上の配偶者ではなかったため、佐々木さんの遺体を葬儀社が引き取りにきた後、彼がどのように弔われ、どこのお墓で眠っているのか知らない。
「彼が亡くなって、先が見えなかったときは本当につらかった。5年間、彼の介護のこと以外何もしていなかったから、それが終わったら糸が切れてしまったように動けなくなってしまって。食事ものどを通らなくて、10キロも痩せてしまいました」
「ずっと彼と2人だけの生活だったんです。彼も私がいればいいし、私も彼がいればよかった。2人だけで十分だったんです」
進藤さんは、彼の死に打ちのめされ、何もできずにいた。しかし、「このままではいけない」と決意し、彼の死から1年後、2人の思い出の地・オーストラリアを訪れる。彼と過ごしたアパートや一緒に散歩した庭園を見て歩くうちに、進藤さんの胸に「これからを生きていくためには、これまでをふり返った手記を残そう」という思いが宿る。
「そのときに朝日新聞社の自分史という企画を知り、本というかたちで私と、そして彼の軌跡を残すことにしました。これまであんなところに行ったなあ、こんな出来事があったなと思いを馳せながら書きつづっていくうちに、心の整理ができて、立ち直っていったんです」

「心が元気になってくると、『今、やれることだけのことをやりたい』と思うようになりました。『インシャラー』——明日のことはわからないのだから、今を大切にしようと思って生きることにしたんです」
そう語る進藤さんが今力を入れているのが、ボランティア活動だ。明治学院大学で開講されているチャレンジコミュニティ大学に通い、ボランティアについて学んだ後、老人ホームへの訪問や高齢者を対象としたアロマトリートメントの施術などを行っている。
「新型コロナウイルスが発生して、先が見えない時代になりました。だからこそ、やりたいことはやりたいときにチャレンジして、自分の嫌なことはしない、嫌な人とは付き合わない、というように生きています。好き嫌いのはっきりした生活ですね」

「最愛の人の死を通して、誰でも必ず最後には死があると痛感しました。電化製品だって永久に使えるものではないんだから、それと同じように人間の身体だって永久に保てるわけではない。だからこそ、生きているときを大切したいし、そのために好きなことしかしない、と徹底しているんです」
まだデータがありません。


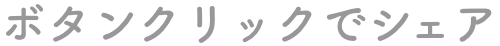
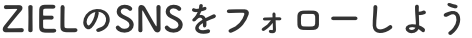




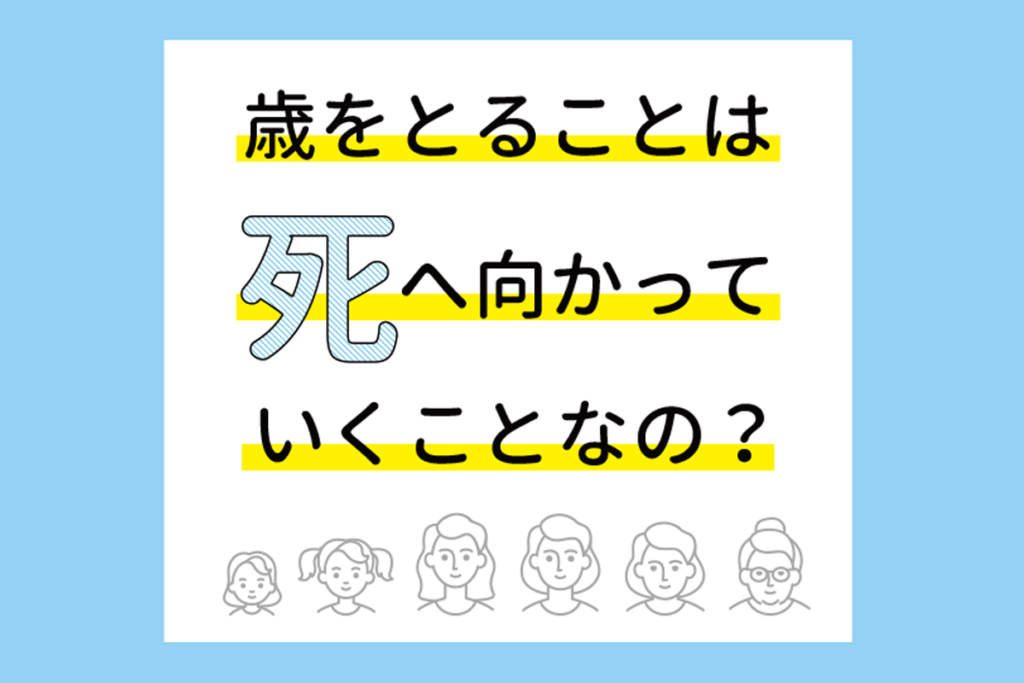








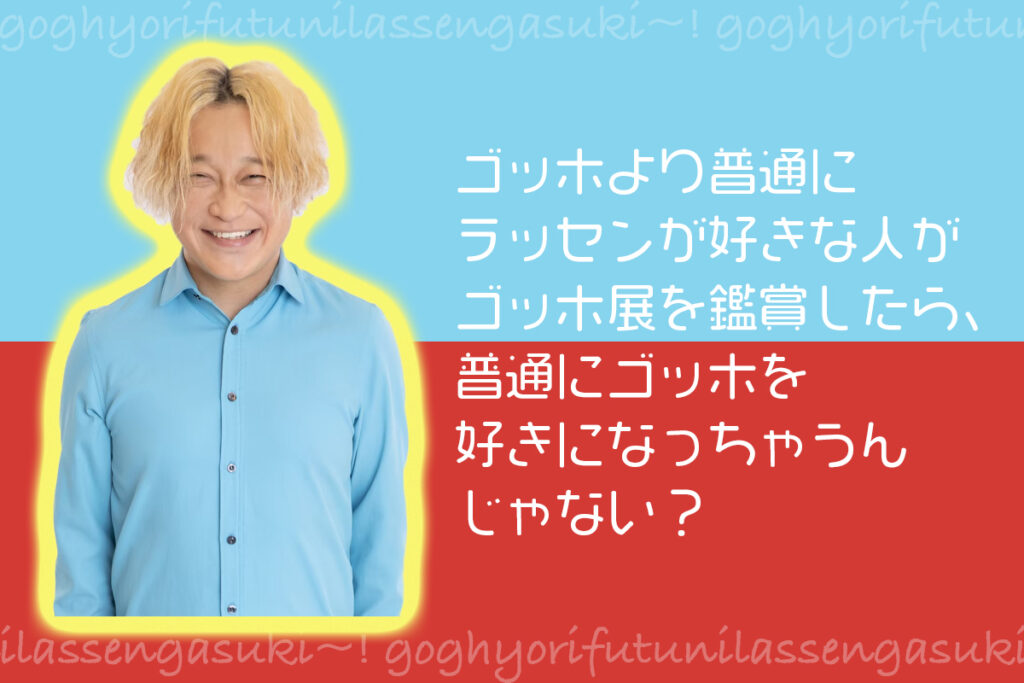





進藤君枝さんにコンタクトを取りたいのですが?どのようにしたら可能でしょうか?