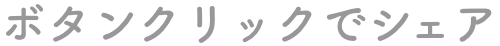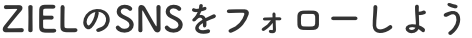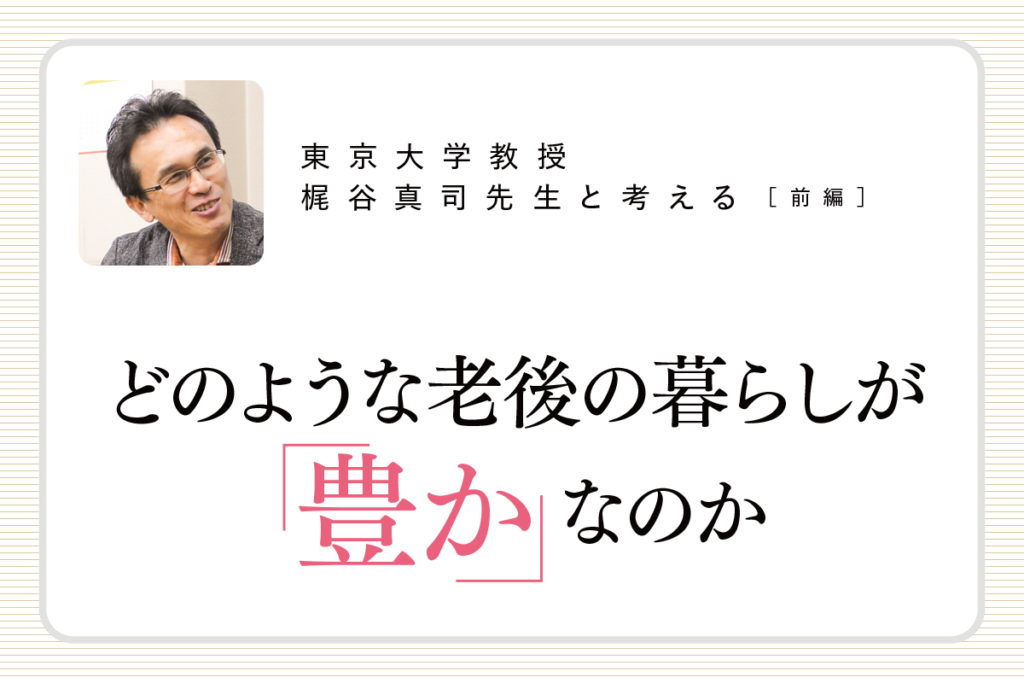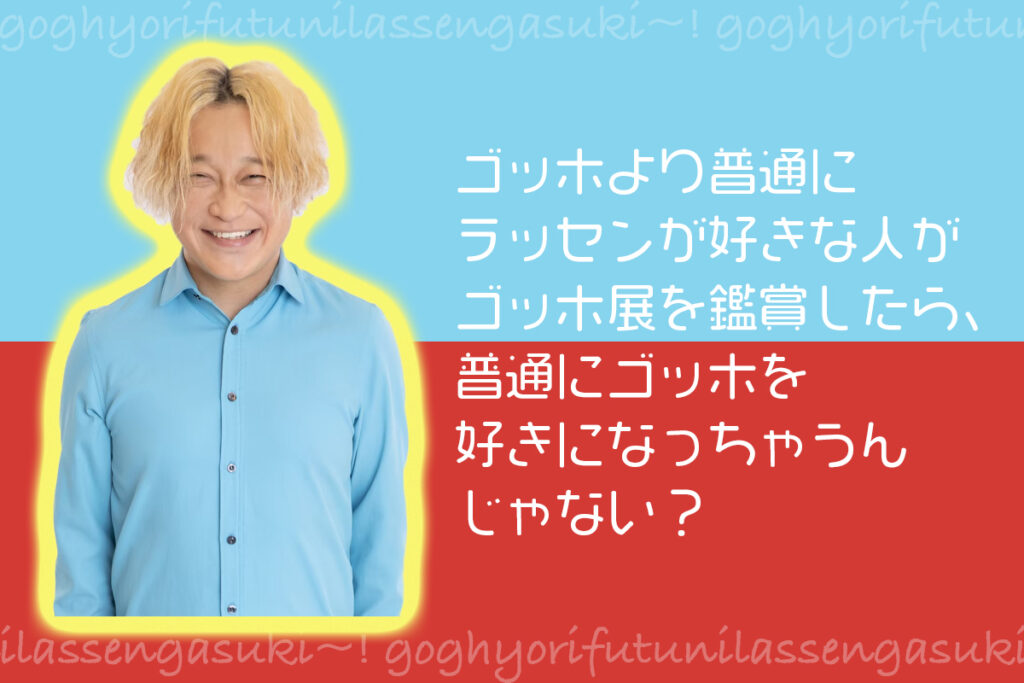【北條和子さん・76歳】父の言葉を胸に子どもたちと走り回った46年間の教育職
とにかく前に進む、それが私の人生

取材・文:出口夢々
60年生きた女性にはいろいろな人生がある。そして、女性一人ひとりはそれぞれ自分の人生を背負い、生きている。若くして家庭を持った人、働きながら子どもを育てた人、社会で戦い抜いた人——。そんな女性たちが経験した、人生の「酸い」も「甘い」を紹介する連載企画「60年、酸いも甘いも讃えたい」。
第3回目は、東京都港区にお住いの北條和子さん(76歳)にインタビュー。厳格な父のもとで育った幼少期や、46年間勤めた仕事で得たこと、そして退職後の暮らしとの向き合い方について話を伺った。
東京都港区にお住まいの北條和子さん。7年前、家族の仕事の都合で一時上京した北條さんは、生まれてから退職をするまでの67年間を東北で過ごした。大きな農家の家庭で生まれた北條さんが幼いころよく目にしていたのが、両親の苦労する姿だ。

北條さんが生まれた翌年の1945年、GHQの指揮のもと農地改革が行われた。政府が強制的に農地を安値で買い上げ、実際に耕作していた小作人にその農地が売り渡されたのだ。北條さんの親が管理していた土地も政府に安値で買い上げられ、小作人の手に渡っていった。
「父は軍人だったのですが、戦地から『農地改革がなされるようだ。どんなに土地を荒らしてもいいから小作人は立てないで、家の人だけで農作業をするように』と母に連絡をしたそうです。母はその父の言葉どおり、必死に土地を守るわけですよ。いろんな人にご奉仕いただいたり、近所の方にお手伝いをしていただいたり。その結果、守り通せた土地もありましたが、小作人に渡ってしまった土地もありました」
その後、戦地から戻ってきた父の市治さんは、小作人に渡った土地のうち、条件のよいところを取り戻すために奔走した。当時は食糧難の時代。ある程度まとまった土地を買い戻せた後は、奉公として家を出ざるをえなかった少年、少女を預かり、働いてもらう代わりに衣食住を提供していた。自立して生活できるようになるまで彼らを育て、家を出るときにはたんす1竿や着物を持たせた。
「物心ついたときには、お手伝いさんが常時5、6人はいました。働き手として来てもらっているお手伝いさんたちにきちんとした食事や服を用意するのが、両親は大変だったようです。うちの人たちはボロボロの服を着ていました。お盆とお正月には必ず浴衣や下駄などを買い与えられているお手伝いさんたちの姿を見て、『いやあ、奉公に行けるっていいな』と思ったものです」
そのような幼少期を過ごした北條さんが常に意識していたのが、父親の存在だ。
「小さいときは厳しい父のことが嫌いでしたね。厳しいというのは、『食べたお茶碗は自分で下げる』『靴は揃える』みたいな、生きていくための基本的なことが厳しくて。『片づけなさい』ともろに言うならいいんですけど、『ちょっとやることあるよね』と、考えさせるような物言いをするんです。あれしなさい、これしなさい、という指示はないのですが、むしろ考えながら動かなきゃならない。それが窮屈でした」
だが、北條さんが成長するにつれ、父親が教えてくれたことの重要さをわかるようになり、そのわだかまりがとけていった。その後の北條さんが46年間勤め上げる教育職に就いたのも、父の市治さんの言葉に影響されている。
「『どのような時代が来ても、きちんとした教育がなされていれば生きていける』という父の言葉は今になっても忘れません。父は、どんなに貧乏してても、着るものがみすぼらしくても、学校の教科書だけは新品のものを使わせてくれていたんです」
「私たちが子どものころは教科書は無償じゃないんですよ。買わなきゃならないんです。そうすると、教科書を買えない家庭もあるんですよね。だから、周りの子たちは「お姉さんの教科書を引き継いだ」とか「国語の教科書はお隣さんからもらった」とか言って。でも、私たちは教科書だけは全教科まっさらなのを使わせてもらった。それはやっぱりうれしかったですね。せっかく用意してもらた教科書。であれば真っ黒は言い過ぎだとしても、書くところがなくなるくらい書き込んでいこう、と。『好きなだけ書き込んで勉強しなさい』という父親の言葉がずっと胸のなかにあり続けましたね」
その言葉は、大学に進学した北條さんの糧になった。「取れるものは取ろう」と貪欲にさまざまな資格をとり続けた。その資格のひとつが、教員免許だ。
北條さんは1970年、小学校の先生として教壇に立つ。

「やっぱり仕事ですから、一概に『楽しい』と言えないこともありました。でも、一緒に遊んだり、飛んだり、泳いだり、走ったり、サッカーしたりということが好きでした。子どもに悪い子はいないので、どんな悪さをしている子どもでも話をすれば素直でかわいいんですよ。もちろん、悪いときは徹底して怒りますけど、手をかければ結果が見える。それが楽しかったですね」
凝り性だという北條さんは、先生たちが参加する研究会での公開授業にも手を抜かなかった。そのため、家に帰るのは夜20時、21時過ぎ。自分が好きな仕事を続けられるよう、子どもを安心して見てもらえる姑のいる家庭に嫁いだ。
「私が若かったころ、結婚する条件として『家付き、カー付き、ババ抜き』という言葉が流行ったんですよ。家があること、車があること、そしてお姑さんがいないこと。これが流行語のようになって、ほかの多くの女性がけっこう意識していましたね。でも私は『家付き、カー付き、ババ付き』で探しました。自分が仕事をしたかったから」
自分は家庭に収まらず、結婚しても子どもを産んでも働きたい——。そう思うようになったのも、やはり父・市治さんの影響だ。
「今思えば、父親は先見の明があったように思います。『これからは女性は ‟おかえりなさい” ‟いってらっしゃい” と三つ指をついて言う時代ではなくなる。自分で女性が働かなければならなくなる時代だから、教育は身につけなさい』と、仕事をするように仕向けられましたね。どんな世の中が来ても、たとえ結婚した相手が亡くなっても、自立できる力はつけなければならないと言われていたので、自分が好きな仕事を続けるには子どもを安心して見てもらえる家族が一番、と思って、『ババ付き』のところを選びました(笑)」

「働き盛りのときはやればやるだけ結果が出ました。授業に力を入れたら、その分生徒の力が伸びるんです。授業で版画や絵画を制作した際に生徒の作品をコンクールに出展したのですが、それがすばらしい賞をいただいて。その結果、東京の出版社から『生徒の作品と先生のコメントを全集に載せないか』とご依頼があって、それらが本に掲載されたりして。そうすると、みんなの気持ちが高揚しますよね。子どもも親も学校全体の雰囲気がよくなって、ほんとに楽しいなと思って暮らしてきました。なのでね、私は仕事一筋で生きてきたと思うんです」
仕事は、「お金のため」だけでは続かない。「この仕事が好きだ」「同じ仕事をするなら楽しく働こう」と思うことで続けることができる。そう語る北條さん。今でも教え子たちとの交流は続いている。
「初任の学校で受け持ったクラスにいた子と今でも関係が続いています。50年前に担任したクラスの子なので、子と言っても、今はもう定年退職をしている年齢なんですけど、『先生、あわびが獲れました』『ウニが獲れました』などと言って、贈り物をしてくれるんです。つい1週間くらい前にも送ってくれましたね。『もういいわよ』と言うんですけどね。『やれるまでやります』って、『先生への恩返しです』と言って。私は怒ってばっかりだったのに」
「話を聞くと、『ある先生に怒られていたのを、北條先生だけは助けてくれた』と言うんです。ほかの先生は見て見ぬふりをしていたけど、私はそこに入って『どうしたの? 理由があるでしょ?』とその子に聞いて、仲裁したんですね。それがうれしかったって。そういうことを何十年も覚えているんですよ。子どもを侮ってはいけないですよね」
そう語る北條さんが、教員という仕事から学んだのは思考を切り替えることの大切さだ。
「悩んだことももちろんありました。上司とそりが合わないとき、親の介護が始まって仕事との両立がむずかしくなったとき——。そんなときに、どう切り替えていくかが大事なんです。この切り替える力が生きる力に直結するなと思いましたね。悩んでいると、おいしいものを食べたっておいしいと感じなくなりますし、何をしたって楽しくなくなる。
人生、楽しいことばかりではないですよ。『えっ』と思うことが起こったときにどう切り替えるか。その切り替えるコツを覚えれば、少々のことが起こっても大丈夫なのかなと、46年間仕事を続けてきて思えるようになった――そんな気がしています。」
「私は『たられば』という言葉が好きではないんです。『あのときやっていれば』とか『あのときこうしていれば』という後悔をしたくないんです。なので、困ったとき、落ち込んだとき、悩んだときにどうするか。そうしたときに切り替える。『あのときはあのときでこれがいいと思って結論を出したんだから、これでよかったんだ。前に進むしかない』と切り替える。そういうふうに生きてきました。後悔するのが嫌なんです」
7年前、仕事が忙しい娘さんの子育てをフォローするために東京に上京した北條さん。定年を迎え、その後7年間非常勤講師として勤め上げた矢先の上京に、友人たちからは「やっと自分の時間ができたのに……。」という声もかけられた。しかし、孫から元気をもらいながら楽しんで生活していると語る北條さんの顔は溌剌としている。

「私の状況を『大変』と評価するか、『いやあ、楽しそうだね』と評価するかのは、意識の違いによって分かれると思います。明治から昭和にかけて活躍した医師の後藤新平の『自治三訣』にありましたね。『人の世話をする。人の世話にはならない。報いを求めない』というのは、現代でも大切だと思うんです」
「人のせいにはしたくない。やっぱり人のせいにするだけじゃなくて、自分をふり返ってみて、自分の課題をどう解決していくかを考えるのことが大事だと思います。自分の課題を解決しないで他人のせいにしていては何も始まらないんですよ。でも、人間ひとりで全部は解決できないので、なんでも話し合える兄弟だったり友だちはほしいですよね。相談相手とか。そうやって前に進むのが、私の生きる道だと思っています」
上京後、シルバー人材センターに登録し、隙間時間に仕事をしてみたり、パソコンキータッチ検定の受験や朗読会への参加、墨絵やちりめん細工の制作など、可能な限りさまざまなことに挑戦し続けている。
「やっぱりね、人間、年齢がすべてではないですよ。私が通っているヨガ教室に98歳の旦那さんと、92歳の奥さんのご夫婦がいるんです。そういう方たちに会うと、刺激を受けますよね。5年前に、私と同時期にその教室に参加するようになったのですが、旦那さんは当時93歳。その歳で見ず知らずの『新たな場所』に入るって、すごいですよね。この意識の高さですよ。すばらしいですよね」

「『もう年なんだから』じゃなくって、新しいことに向いていこうと思える気持ちを持てるかどうか。それが大事だと思っています。新しいことに興味を持てるかどうかで、老化の仕方が違うと思うんです。興味とは、すなわち『向上心』ですよね。ですので、少し億劫な気持ちがあったとしても、『やってみよう』とか『挑戦してみよう』と動き出すようにしています」
そう語る北條さんは、新型コロナウイルスの影響でヨガ教室の利用が制限されても「コロナ禍だからこそできることがある」と考えた。そのときに始めたウォーキングやストレッチも今では生活の一部だ。
「死ぬまで挑戦だと思います。76年生きてきて、そんな気がしているんです」
まだデータがありません。