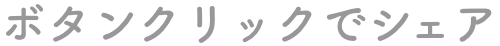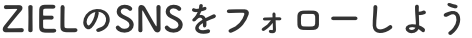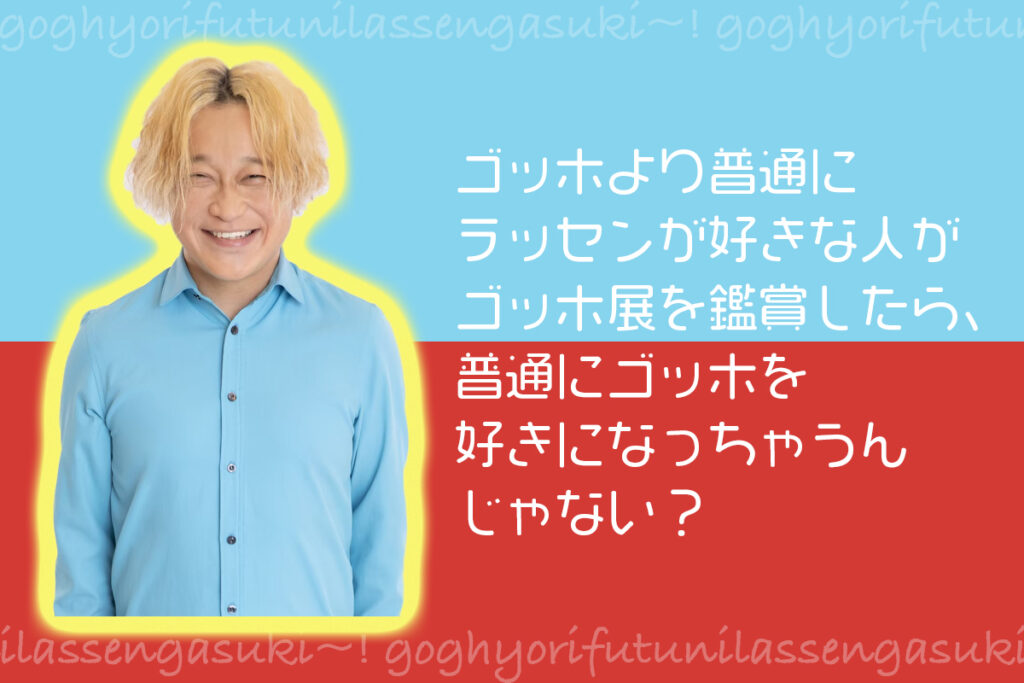「自伝」の書き方
長い人生を本にまとめるために、まず行うべきこと

文:金丸信丈
人生の節目を迎えたある日、これまでの長く、つらく、楽しかった生涯を1冊の本にまとめてみたい――。
「自伝」を書こうとしている方々に向けて、その方法をお話します。
ZIEL編集部の書籍編集者としての経験が、みなさんのお役に立てればうれしいです。
いろいろな本をつくってきました
編集者として、長く書籍、ムック、雑誌の制作に携わってきました。
扱ってきたテーマはあまりに雑多で、一口に「こんな本をつくってきた」とは言えません。しかし、それゆえ、いろいろな本のつくり方を勉強する機会に恵まれました。
本のつくり方は、本の「つくり」によって異なります。
まず、当然ながら、文章を中心にした本。
そして、写真やイラストを中心にした本。
ほかにも、図解を中心にした本。

編集者は、本の制作を開始するにあたって(もしくは開始する前にも)、色々な人に声をかけます。
本のつくりごとに、声をかける人たち、打ち合わせ内容が変わります。
ここでは、「自伝」で多く採用される形態である文章中心の本のつくり方について話をしていきます。
まず考えるべきは「なぜ書くのか」
文章中心の本はほかの素材の助けを借りない文章一本勝負ですから、編集者として、少なくとも私個人としてはもっとも緊張する体裁です。
文章のみで勝負するわけですから、文章の構成が本の生命線となります。
いかに文章をつないでいくかという「流れ」もそうですが、まずは構成する要素、つまり「何を書くのか」について、吟味します。
「何を書くのか」を考える際、まず考えてほしいのは「なぜ書くのか」。書く理由がないままにつくられた本は、この世に一冊もありません。
「印税が入って金を儲けたいから」「有名になりたいから」といった理由を聞くこともありますが、これから自伝を書こうとしている方々の動機は、そうではないでしょう。
そもそも、出版でお金は儲かりません(笑)。出版業界に身を置く者として、大きな声で言えることではありませんが……。誤解なきように急いで補足すると、10万円、100万円を稼ぐには、あまりに効率が悪いという話です。
編集者としてのキャリアを積み始めたころは、時給が最低賃金を割っていることもしばしばありました。とは言え、あくまで「換算すると」です。月給制ですから、給与明細の見かけ上はきちんともらっています。

今でこそ、働き方革命などで正常化が進んでいますが、かつての編集者たちは、狂ったような生活をしている人も多くいました。「夕方から本気出す」という “編集者あるある” があったりしますが、夕方から出社して始発で帰る、とか。私自身も昼過ぎに出社して終電で帰ることが “定時” になっていたり、家に帰るのが面倒で3日連続で会社に泊まったり……。深夜午前1時に、まだ会社にいる同僚と酒を飲みに行って、そのまま会社に戻って寝たりなどしていました。さすがに当時の会社の社長に怒られましたが、バレないように次はサウナに泊まるようにしたり……。もはや堅気とは言えない仕事ぶりでした。
若いときは、それが「かっこいい編集者」だと思っていたわけです(笑)。ご多聞に漏れず、身体を壊して1カ月ほど入院しました。私が担当していた本を代わりに誰かが校了してくれているのではないかと淡い期待を抱いて退院したところ、入院前と寸分違わぬ状態で紙面が置かれていました。入院していたときよりショックでした。
と、これ以上の昔の苦労話が続くようであれば、私が編集担当ならバッサリ切るでしょうから、このあたりで自重します。
少々余談が過ぎました。話を戻します。
自伝を「なぜ」書くのか――。
「これまでの人生を振り返りたい」
「ある特定の誰かに伝えたい」
「感謝の気持ちを伝えたい」
「いろいろな人に自身の生き様を知ってほしい」
「これからの人生をよりよいものにするための指針をまとめたい」
人によってさまざまだと思いますが、とにかく何かしら理由があるはずです。仮に「作家のような生活を送ってみたい」といった理由であったとしても、自伝を書く理由として十分だと思います。かつてバカげた「かっこいい編集者」の姿を追っていた私としては、十分に共感できます。
どんなことでもいいから、まず書く理由を明確にしてみてください。
「対象読者」は誰か
一般の本づくりの作業も、「書く理由」を考えることから始めます。商業出版においては、もう少し具体的な「書く理由」をつくり込みます。たとえばビジネス書であれば、「口下手なビジネスパーソンが、自分に有利な条件を勝ち取るような交渉をしてほしい」といったもの。
つまり「対象読者」を設定し、その対象読者にどのような「効果」を与えるのか――。ここでいう対象読者とは「口下手なビジネスパーソン」。効果とは「有利な条件を勝ち取る」。
そうした視点で考えると、「書く理由」はより明確になります。
「大好きなあの人たちに、今を生きる幸せを感じてほしい」
「まだ若いあの人たちに、自分の経験談を仕事に活かしてほしい」
「長く苦労をともにした人たちに、いい人生だと感じてほしい」

ここでじっくり考えてほしいのは「対象読者にどうあってほしいのか」という点。「苦労をともにした人に感謝の気持ちを伝えたい」では不十分だと思うのです。
本は、読み手がいてはじめて本として存在すると私は思っています。感謝を伝えるという一方的な気持ちでは、読者不在と言えるでしょう。
ただし――。
ただし一方で「自伝」には、通常の本にはいない大事な読者がいます。
自分です。
「これまで感じてきたことを自分のために書く」というのもまた、自伝のひとつのあり方でしょう。
すると、今しがた読者不在と指摘した「書く理由」を次のように考え直すことができます。
「苦労をともにしたあの人に大していかに感謝しているのか、あらためて自分でかみしめたい」と。
ここで大切なのは、「自分のために」という点を追求しながら書くこと。
少々理論が飛躍しますが、自分のためだけに書いた本は、きっと自分以外の人たちの心を打つ本になると思います。
相手の気持ちを十分に推し量ることなく、一方的に「伝えたい」と書かれた本は、言ってしまえば迷惑です。
このページをご覧の方々は、若かりし日の娘さんや息子さんにいろいろと説教をされたことでしょう。反発されたり、無視されたり、ときには黙って聞いていたりと、反応はさまざまだったと思います。一見聞いていないような姿を見せながら、それでも息子さんや娘さんがしっかりと育っていかれたのは、「○○のような大人になってほしい」と思いながら、説教されたからではないでしょうか。「私のような苦労をしてほしくない」と思いながら説教す人はいても、「私の苦労を伝えたい」と思って説教する人はいないでしょう。
自分以外の人間に――それが長い時間をともにした配偶者であっても、血のつながった子、孫であっても、ものを伝えるというのはそういうことだと思います。
感謝の気持ちを伝える「ありがとう」という言葉。この語源は「有り難し」にあります。文字どおり、「有ることが難しい」という意味です。自分にとって存在することが稀な状態であることを伝えているわけですね。「こんないいことは、私にとってそうそうないよ」と。
かつての日本人は、そうして感謝の意を表していたのです。
現代において、「ありがとう」がこの「有り難し」の意味で使われることはありませんが、自分の気持ちを話すことで、相手にうれしい、よかったと感じてもらえる例として紹介させていただきました。
「あなたがあの日つくってくれた料理はおいしかった」
料理した本人は、この言葉で十分に「つくってよかった」と思ってくれるはずです。「あなたはあの日、おいしい料理をつくった」では、いまいちピンと来ませんよね。
原稿には、結果的に「ありがとう」と書くことにはなると思いますが、それは相手ではなく、あくまで自分のために書くのです。まさに「有り難し」と思いながら。仮に「自分」を「対象読者」と決めたのであれば、そこはブレてはいけません。
構成は「書く理由」からの逆算
ここまで少々理屈をこねくり回してきてしまいましたが、要するに本に必要なのは、一貫性です。その一貫性のひとつとして「自分のため」にこだわって書くことが、「自分以外の人の心を打つ」のです。
対象読者が自分以外にいるのであれば、その場合は、「その対象者」が「どうなってほしいのか」にこだわって書くべきです。

ちなみに、先ほど書いた私の昔話。あれこそ、ダメな原稿の典型です。自分の過去を自嘲気味ながら顧みているようで、その実、その苦労を「ただ聞いてほしい」ために書いているからです。自分で書いておきながら、こういう言い方も何ですが、おもしろくもなんともない。
この一言を言いたいがために書いたわけですが、あのあたりで読むのをあきらめた読者の方もいらっしゃたでしょう。なかなかの諸刃の刃でしたが……ここまで読んでいただいて、ありがとうございます。
とにかく! せっかく書くのですから、みなさんの自伝は、一時的な自己満足になってほしくありません。自身が満足することも自伝の大きな目的ではありますが、書き終えたあとの最初の読者——自分が満足できるかといえば、そうではないのではないでしょうか。
構想を練る——この第一歩は「なぜ書くのか」をとことん考えることです。かつ、第一歩でありつつ、それがすべてです。
構成(目次立て)は、この「書く理由」からの逆算です。
それほどむずかしい作業ではありません。
最後に付け加えるとすれば——。
なぜ書くのか、その理由が「後進の者に伝えることで、彼らによりよい人生を歩んでほしい」ということであれば、それは「生涯をまとめる」という一般に言われる「自伝」のような構成である必要はありません。
「あの日のあの出来事」を中心にまとめてもいいでしょうし、「やり遂げた仕事で得た技術」についてでもよいでしょう。

私は、父親が生涯かけて振り続けた中華鍋に対するこだわりを自伝としてまとめてくれるのなら、ぜひ読んでみたいと思っています。
父親は、私が6歳のときに独立し、自分の店を持ちました。中華料理店です。そのとき2人の弟はまだ保育園にすら通っていませんでした。
その息子3人が全員40代になろうかというとき、体力の限界を感じた父は自らの意思で店を閉めました。今から1年半前、開店から38年が経っていました。競争の激しい飲食店業界にあって、「やりきった」と感じ自らの意思で店を閉めることができる料理人はそれほど多くはないと思います。
料理人の道をまっとうした父親の人生は、父親の矜持は、あの中華鍋に込められているような気がします。
新品の中華鍋を買ってきたときに、まず何を行うのか。私はその段取りについて詳しくはないのですが、とにかくずっと中華鍋を空焼きしていたように記憶しています。その準備は油がよくなじむなど技術的なことなのでしょうが、傍目から見て無駄なように思えるその作業を欠かさないことに、父親の矜持が見て取れます。
なんてことを思い出すと、この前、雑に原稿整理をしてしまった自分をぶんなぐりたい気持ちに……。
しかしながら、私から軽はずみに父に自伝を書けなどとは言えません。
なんだかんだ言って、46歳になった今もなお、やはり父親は怖いですし……。父親が自伝を書くなら、編集は誰かほかの人に任せます。編集を担当された方、完成したら私宛に1冊送ってください。
自伝を書くにあたって疑問などあれば、コメント欄でお寄せください。お一つずつお答えいたします!
まだデータがありません。