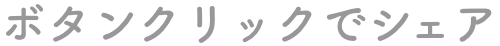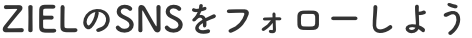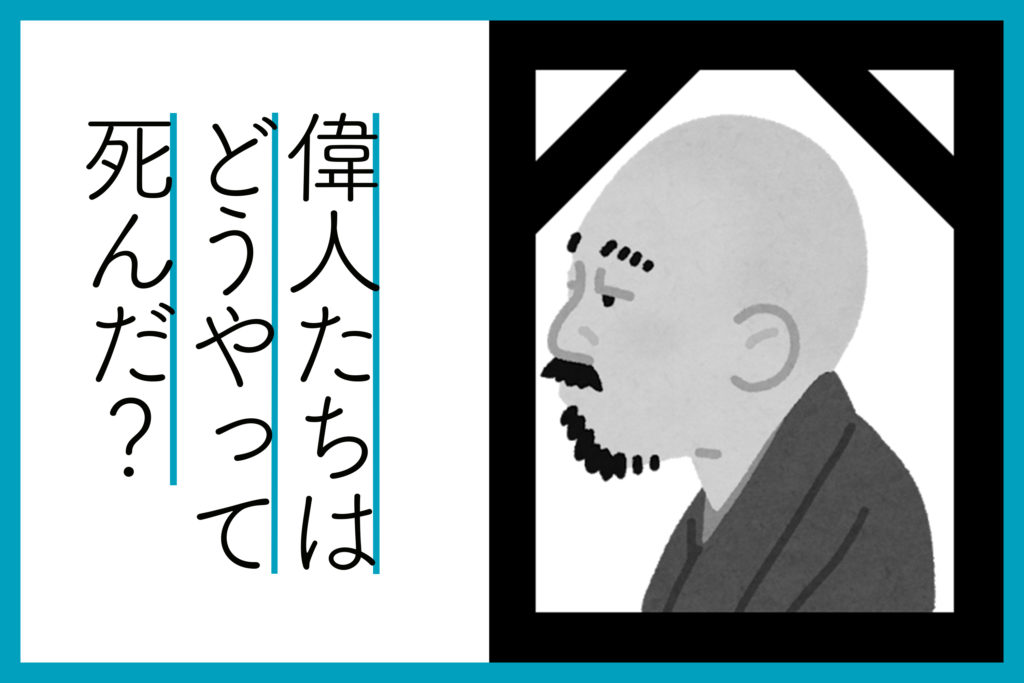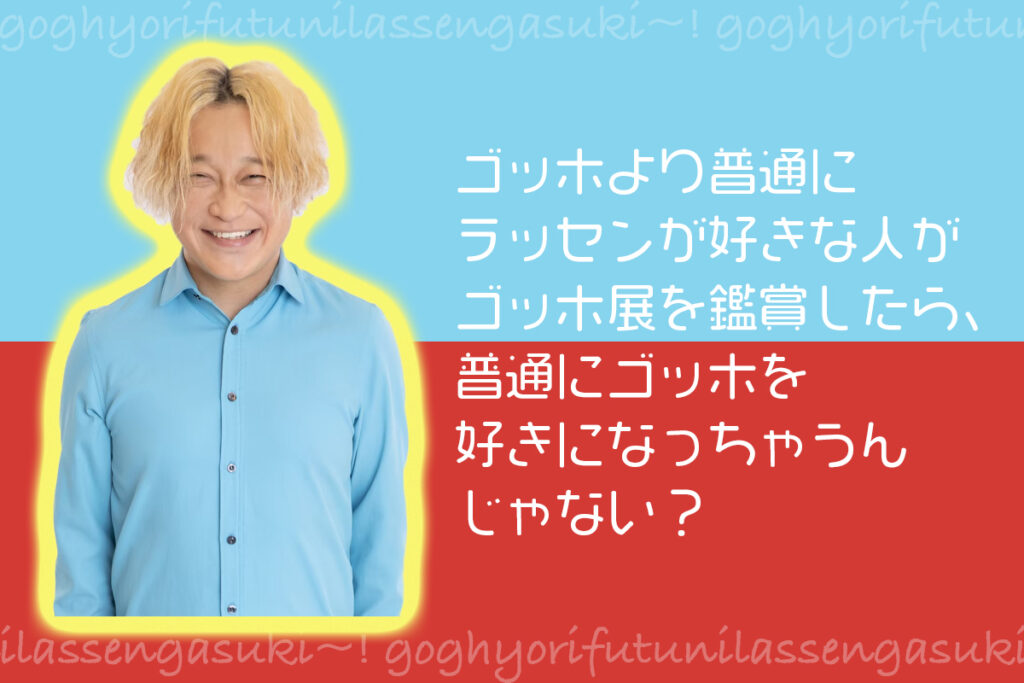【人間VS.新型コロナウイルス】感染症との「勝負」は成立するのか――アルベール・カミュ『ペスト』を読んで
若手編集者もも。12年ぶりの読書感想文を書く

文:出口夢々
新型コロナウイルスの感染拡大が続くなか、日本やフランス、イタリア、イギリスなど世界中でベストセラーとなったのが、長編小説『ペスト』。フランスの作家、アルベール・カミュ(1913-60)が『異邦人』に次いで1947年――約70年前に発表した本作が、現代社会とリンクする部分が多くあると話題を集めています。
そこで、ZIEL編集部・出口が『ペスト』を読み、新型コロナウイルスに「翻弄」されている今の状況を顧みてみました。『ペスト』を読んだ方も、まだ読んでいない方も、出口が疑問に思ったことを、ぜひ一緒に考えてみてください。
*
職業柄、本屋には足繫く通っている。とりわけ欲しい本があるわけでも、毎週心待ちにしている週刊誌があるわけでもないが、今どんな本が棚に並び、人気があるのかが気になって仕方がなく、週に5回も6回も行ってしまうのだ。
新型コロナウイルスの流行が拡大し、緊急事態宣言が出されたときでも、日用品や食料の調達にかこつけて本屋に行っていた。マスクをした人たちがポツポツといるだけの店内。今日もただ目的もなく歩くなかで、平積みにされた1冊の本が目に止まる。
アルベール・カミュの書いた長編小説『ペスト』。
「ああ、あの多くの犠牲者を出した感染症の……」。そう思いながら、手に取った。当然、新型コロナウイルスを連想してしまう。
『ペスト』は、致死率の高い感染症であるペストの脅威にさらされたフランス領アルジェリア(当時)の港町・オランを舞台に、感染症という不条理に直面した際の人間の行動や心理が描かれた作品だ。
*
作中でペストが大流行する港町・オランは、金持ちになるために大いに仕事をする市民によって構成される「全く近代的な町」だ(東京にとても似ている気がする)。町の異変は、ネズミがもたらした。
医師ベルナール・リウーが一匹の死んだネズミを発見したのを皮切りに、町中で続々とネズミの死体が発見されるのである。各建物からごみ箱いっぱいのネズミの死体が発見されるようになったころ、一人の男が不自然な死を遂げる。当初、リウー医師は熱病を疑った。しかし、同じような死を遂げる人間が増加し、それらの人間に現れていた症状が過去に流行したペストの症例にあてはまることから、リウー医師はオランでペストが発生したと判断し、行政へ感染症対策の整備を仰いだのである。
*
なぜ人間はこんなにも愚かなのだろう――。『ペスト』を読み始めて第一に考えさせられたのは、人間の愚鈍さだ。
大多数の場合、別離は、もう明白に疫病の終わるまで終わらないわけであった。そして、われわれすべての者にとって、われわれの生活をなしていた感情、しかもわれわれが十分知り尽くしていると思っていた感情(オランの人々は、前にもいったが、単純な情熱の持主である)が、一つの新たな相貌を呈してきた。妻や恋人に最大の信頼をいだいていた夫や愛人たちが、自ら嫉妬深い男であることを発見した。愛情に軽薄であると自認していた男どもが、変らぬ誠実さを取りもどした。母親のそばで暮らしながら、ろくにその顔をながめようともしなかった息子たちが、絶えず思い出に付きまとう彼女の顔の皺の一筋に、あらゆる不安と心惜しみを注ぐようになった。
……中略……
事実上、われわれは二重の苦しみをしていた――まず第一にわれわれ自身の苦しみと、それから、息子、妻、恋人など、そこにいない者の身の上に想像される苦しみと。アルベール・カミュ『ペスト』宮崎嶺雄訳、新潮文庫(p.100,l.15-p.101,l.12)
ペストが発生した町に最初に課せられたのは、町の封鎖だ。その町に住む者も、旅行で一時的に滞在していた者も、事情などみな関係なしに、オランに「幽閉」されることになる。そして、ちょっとした用事でその町を離れていた者は、オランへ、そして愛する人の元へ戻ることができなくなった。つまり「あたり前」が喪失したのである。
感染症という「不条理」によって、それまでのあたり前を失わざるを得なくなったわけだが、失ってからでないと気づけない「大切なもの」は、当人にとってはたして本当に大切なものなのだろうか。不条理によってでしか気づけない「大切さ」など、まやかしものでしかないのではないか。私は疑問を抱いて仕方がない。
町が幽閉され、自分の意思が阻害された状況だからこそ、他人を思う気持ちが発生したのかもしれない――。さまざまなものが限定された状況において、はじめて明確な感情として「愛」が自身のなかに芽生えたのかもしれない――。そう自分の感情を疑いの目で見る者が『ペスト』において一人も存在していないことに、非常に驚かされた。みな、自分の感情を過信しすぎではないか?
仮に、不条理と直面したときに抱いた感情が、まやかしものでない、真物だったとしよう。そうすると、次に私は、大切なものを大切なものとして扱えなかったかつての――ペストが流行る前の「日常」に対して疑念を抱いてしまう。
行動が制限されると、愛している人へ思いが募るだけでなく、愛している人が隣にいた「日常」にも思いを馳せてしまう傾向にあるが、働いてばかりで大切な人を大切だと認識できない「日常」を恋しく思う理由がわからない。「失った」から恋しく思うだけで、以前は本当にそれを必要としていたのだろうか。
*
「わからない」といえば、緊急事態宣言中、街中でたまに見かける「みんなで力を合わせて新型コロナウイルスに勝とう」というポスターだ。
「コロナに勝つ」とは……? 愚鈍な私はその言葉の意味をまったく理解できなかった。新型コロナウイルスは日常生活を営むうえで確かに脅威ではあるが、いつ「勝負」が始まったのか。新型コロナウイルスに勝つために生活様式を変えることは、戦っているというよりも、防御しているだけでないのか。新型コロナウイルスと人間のあいだに「勝ち負け」があるのだとすれば、ワクチンが開発され、それによりウイルスにかからなくなった(感染しても症状が出なくなった)ときの状態を指すのではないか。だとすれば、勝負をしているのは医療従事者だけなのでないか――。駅のエスカレーターに貼られたポスターを見て、そう考えずにはいられなかったのである。
しかし、この「ウイルスに戦う」という表現は『ペスト』においても見受けられた。
こういう隊が作られたことは、市民たちが一層深くペストのなかにはいり込むことを助け、病疫が現に目の前にある以上は、それと戦うためになすべきことをなさねばらなぬということを、一部分、彼らに納得させたのである。
アルベール・カミュ『ペスト』宮崎嶺雄訳、新潮文庫(p.194,l.5-7)
パリから取り寄せた血清が何の効果も発揮しないまま、オランでは相変わらずペストが猛威を振るっていた。来る日も来る日も人が亡くなり、亡くなった人を埋葬するための職員が作業中にペストに感染し、亡くなってしまう。ペストの影響でこれまでどおりの仕事がなくなり、働く場所がなくなった人々は貧困とも戦わなければならなくなったため、埋葬の職員に欠員が出るとそこへ働きに行かざるを得ない。また、行政をストップさせないためにも率先して保健所へ手伝いにいかなければならない。つまり、ペストという不条理は人間に対して「平等」に不安を与え、そこへ「奇妙な連帯感」を生じさせたのである。
奇妙な連帯感が生じているのは、オランだけではない。今の日本でも同様だ。きっと、駅に貼られていたポスターは「みんなで力を合わせて新型コロナウイルス(という不条理)に勝とう」という意味だったのだろう。これまでの日常をなるべく失わないために、一人ひとりができることを行おうという意味だったのだろう。この意味になぜ気づけなかったのか私は猛省すべきだが、それはまた別の機会にしよう……。
*
連帯感が生まれた後、その連帯感とは関係なくオランではペストが終息したわけだが、日本ではどのように新型コロナウイルスが終息していくのだろうか――。そして、終息した後にはどのような「日常」が待っているのだろうか――。『ペスト』で描かれている「取り戻された日常」を頭の片隅に置きながら、思いを馳せている。
まだデータがありません。